「わたしって集中力ないなぁ…」
デスクワークをしていると、すぐに集中力が途切れてしまうことはありませんか?こんなとき、多くの人が自分の集中力の無さに嫌気がさすものです。
しかし、集中力の無さを自分の能力のせいにするのは少し待ってください。
実は、集中力はデスク環境次第で大きく改善します!普段のデスク環境を少し変えるだけで、集中力が続くようになる可能性があるのです。
本ページでは、そんな集中力が続くデスク環境の作り方を詳しく解説していきます。今日からできる簡単な方法ばかりですので、ぜひ実践してみてください。
集中力が続かないデスク環境の原因
集中力が続かない原因は、デスク環境に潜んでいる場合があります。まずは、あなたのデスク環境の問題点を見つけていきましょう。
悪い姿勢になりやすい
集中力が続かない大きな原因のひとつは、悪い姿勢になりやすいデスク環境です。
はじめにデスクの高さを確認してみましょう。デスクの高さが合っていないと、自然と前かがみになり、首や肩に余計な負担がかかります。
また、PCモニターの位置も重要です。画面が低すぎると首を前に出す「ストレートネック」の原因になり、高すぎると首を反らせて頸椎に負担をかけることになります。一般的な理想的な視線の角度は、やや下向き(10〜15度)とされています。この角度から大きく外れると、首の筋肉が常に緊張状態となり、集中力が低下していくのです。
さらに、長時間同じ姿勢で座ることも集中力が続かない原因になります。固定された姿勢が続くと血流が悪くなり、酸素や栄養素が脳に十分に行き渡らなくなります。その結果、思考力や集中力の低下につながっているのです。これらの身体への負担は、気づかないうちにあなたの集中力を奪っています。
余計なものが多い
デスクの上に余計なものを置きすぎると集中力が低下しやすくなります。
デスクの上に色々なものが置かれていると、視覚的な情報過多になり、脳は常に余計な刺激を処理しなければなりません。書類の山、使っていない文房具、食べかけのお菓子など、作業に直接関係のないものが視界に入るたびに、脳はそれらに注意を向けてしまうのです。
研究によれば、外界から入るうちの80%は視覚によるもので、余計な視覚情報は脳内の処理を無駄に浪費します。(※1)特に現代社会において集中力が続かない「余計な物」となっているのが、スマートフォンです。
通知音やバイブレーション、さらには画面が点灯するだけでも、私たちの注意は瞬時にそちらへ向かいます。一度スマホを手に取ると、平均して23分間は元の作業に集中できないというデータもあります。
これは「タスクスイッチングコスト」と呼ばれ、脳が別のタスクに切り替わるたびに生じる負担です。
また、デスク周りのケーブル類が絡まっていたり、引き出しの中が整理されていなかったりすると、必要なものを探す時間が増え、作業の流れが途切れます。こうした細かな中断の積み重ねが、結果的に大きな時間のロスとなり、集中力の持続を妨げているのです。
照明・音・温度環境が悪い
デスク環境とは、デスクの上や椅子だけではありません。
照明・音・室温などすべての環境がデスク環境であり、これらも集中力が続かない原因になっていることがあるのです。
照明は、暗すぎると目が疲れやすく、脳も活性化しにくくなります。一方で、直射的な明るすぎる光や、画面との明暗差が大きい環境も目への負担となり、長時間の集中を妨げます。
特にブルーライトを多く含む照明は、目の疲労だけでなく、夕方以降は睡眠ホルモンの分泌を抑制し、夜の休息にも悪影響を及ぼすことがあるのです。
音は、突発的な騒音や人の会話が最も集中力を乱す原因のひとつです。特に言語を含む音(会話や歌詞のある音楽など)は、無意識のうちに脳がその内容を処理しようとするため、作業の邪魔になります。
完全な静寂も逆に小さな音が気になりやすく集中力が低下してしまうでしょう。
温度も集中力が続かない原因になります。
暑すぎる環境では血流が皮膚表面に集中し、脳への血流が減少します。寒すぎる環境では体が緊張し、余計なエネルギーを消費します。
加えて、湿度が低すぎると目や喉の乾燥を引き起こし、不快感から集中が途切れがちになるのです。これらの環境要因は、小さな問題に思えても総合的に集中力が続かない原因になるため軽視できません。
集中力が続くデスク環境の作り方
集中力が続かない原因をお伝えさせていただきましたが、ここからは具体的な改善策をご提案していきます。
姿勢に良いデスク&チェア
集中力が続くデスク&チェアで大切なことは「疲れにくい姿勢」を作りあげることができるかどうかです。
まずは、デスクと椅子の高さの関係を見ていきましょう。
座った状態で、デスクに手を置いたとき肘が90度に曲がり、手首が自然とキーボード上に置ける高さが理想的です。この姿勢では、肩の力が抜け、首や背中への負担が軽減されます。具体的には、椅子に座った状態で、デスクの天板が肘の高さと同じかやや低いくらいが最適です。
足裏がしっかりと床に着くことも重要なポイントです。
足が浮いていると、無意識のうちに体が前傾し、腰への負担が増大します。身長に合わせて椅子の高さを調整し、それでも足が床に届かない場合はフットレストを使用しましょう。理想的な姿勢では、膝が90度程度に曲がり、太ももがほぼ水平になります。
PCモニターの位置も、長時間の集中作業には欠かせません。
モニターの上端が目線と同じか、やや下になるよう調整しましょう。画面を見るときに首が自然とやや下を向く角度(10〜15度)が、頸椎への負担を最小限に抑えます。モニターとの距離は、腕を伸ばした距離(約50〜70cm)が目安となります。近すぎると目の疲労を早め、遠すぎると前傾姿勢になってしまいます。
余計なものを減らす
余計なものを減らして作業に集中できる環境づくりをすると、集中力が続きやすくなります。
集中力を高めるデスク環境のポイントは、視覚的な情報を整理することです。まずは、必要最小限のものだけをデスク上に置くミニマルなアプローチを試してみましょう。
具体的には、現在取り組んでいるタスクに必要なものだけをデスク上に出し、それ以外は引き出しや収納スペースにしまいます。成功者の多くが実践する「クリアデスク」と呼ばれる手法で、作業終了時にはデスクを完全に片付ける習慣をつけることで、翌日の集中力向上効果も期待できるのです。
デジタルデバイスの管理も重要です。
スマートフォンは集中力を削ぐ最大の原因となるため、作業中は手の届かない場所に置くか、別の部屋に置きましょう。どうしても手元に置きたい場合は、通知をすべてオフにし、画面を下向きにして置くことで、視覚的な誘惑を減らせます。さらに、「Forest」などの集中力アプリを活用すれば、スマホ依存の克服にもつながります。
照明・音・温度を調整する
最適なデスク周辺環境は、集中力を最大限に持続させてくれます。
まずは照明から。
自然光が最も目に優しく脳を活性化させますが、窓からの直射日光はまぶしさや画面の反射を引き起こすため避けるべきです。理想は、窓が横にあり、間接的に光が入る環境が最適ですが、自然光が十分でない場合は、青みがかった白色の照明が日中の作業に適しており、夕方以降は電球色に切り替えることで、体内時計を乱さずに仕事ができます。
また、「一般的な事務作業」については 300 ルクス以上、「付随的な事務作業」については 150ルクス以上の照明が望ましいとした基準が、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3
年厚生労働省令第188号)」が公布されています。(※2)
特に注目したいのが、ブルーライトを軽減する間接照明です。直接光源を見ないタイプの照明(間接照明)は、まぶしさを抑えつつ部屋全体を明るくできます。デスクライトは、LEDでも目に優しいブルーライトカット機能付きのものを選ぶと良いでしょう。
光の向きは、手元を明るく照らしつつ、画面に反射しない角度に調整することがポイントです。調光機能があり、作業内容や時間帯に応じて明るさを変えられるものが便利です。
音環境も集中力に大きく影響します。
例えば、カフェなどで作業がはかどるように、完全な静寂よりも、一定のバックグラウンドノイズがある方が集中しやすい傾向があります。ご自身で黙々と作業ができる環境にある場合は、自然と聞き流せるBGMのなかでの作業がおすすめです。
最後に温度環境です。
研究によれば、知的作業に最適な室温は20〜25℃程度とされており、温度が高過ぎると眠気を誘い、低いと体が緊張して集中力が低下すると言われています。湿度は40〜60%が理想的で、乾燥しやすい冬場は加湿が必要です。
エアコンの風が直接体に当たると、局所的な冷えや乾燥を引き起こすため、風向きの調整にも配慮しましょう。季節によって変わる環境に合わせて、薄手のブランケットやひざ掛けを用意しておくと、快適な状態を維持しやすくなります。
これらの環境要因を最適化することで、脳は余計なストレスから解放され仕事に集中しやすくなるでしょう。
集中力を続かせるデスク環境以外の「+αの方法」
集中力を持続させるためのデスク環境を整えたら、作業の仕方自体を工夫することで、さらに集中力を高めることができます。
休憩のリズムを整える
集中力を長時間維持するためには、休憩のリズムを整えることが大切です。
様々な休憩の方法があるなかでも、効果的な方法のひとつが「ポモドーロ・テクニック(※3)」と呼ばれる時間管理法です。具体的な方法は、25分間の集中作業と5分間の休憩を1セットとし、これを4回繰り返した後に15〜30分の長めの休憩を取るというサイクルで作業をします。
この方法のメリットは、脳に「あと少しで休憩できる」という安心感を与えながら、集中力を維持できる点です。タイマーを設定することで、「今はこの25分間、このタスクだけに集中する」という明確な意図が生まれ、他のことを考える余裕を脳に与えません。また、決められた休憩時間をしっかり取ることで、次の作業セッションへの集中力が回復します。
さらに実践して欲しい休憩方法は、1時間に1回は必ず立ち上がるという方法です。
長時間座り続けることは、血流を悪くするだけでなく、腰や背中への負担も増加させます。立ち上がって簡単にストレッチをするだけでも、全身の血流が改善され、脳への酸素供給量が増加するため集中力が続きやすくなります。
会社勤めの場合、多くの方が自身で休憩のコントロールが困難のはずです。それでも、1時間に1回は席を立つということだけは実践して欲しい休憩方法です。
こまめな水分補給
集中力を維持するためには、適切な水分補給が欠かせません。
人間の脳の約75%は水分でできており、わずか2%の脱水でも認知機能が低下するというデータがあります。デスクには常に水を用意し、意識的に少しずつ飲む習慣をつけましょう。
理想的には、カフェインやシンプルな水のどちらか一方に偏らず、バランスよく取り入れることがポイントです。カフェインを含む飲み物(コーヒーや緑茶など)は適量であれば集中力を高める効果がありますが、取りすぎると逆に神経が高ぶりすぎて集中力が散漫になることもあります。
一般的に、午後3時以降のカフェイン摂取は夜の睡眠の質を下げる可能性があるため注意が必要です。代わりにハーブティーや白湯などを取り入れると、水分補給しつつもカフェインの過剰摂取を避けられます。
適度なストレッチ
デスクでできる簡単なストレッチも、集中力維持に効果的です。
特に肩回りの緊張を解消する「肩甲骨はがし」は、デスクワーカーに最適なストレッチのひとつになります。椅子に座ったまま、両腕を胸の前でクロスさせ、息を吐きながら背中を丸め、息を吸いながら胸を開くように腕を横に開きます。これを5回ほど繰り返すだけで、肩こりの予防と血流改善の効果が期待できます。
また、「首のストレッチ」も効果的です。
頭を右に傾け、右手で頭を軽く引っ張りながら15秒キープし、反対側も同様に行います。ストレッチの注意点は適度に伸ばすことです。過度なストレッチは症状の悪化を招くリスクを高めてしまうため注意しましょう。

まとめ
集中力が続くデスク環境の作り方を解説を解説させていただきました。
集中力が続くデスク環境を作るためには、まず自身のデスク環境を見直す必要があります。
- 悪い姿勢でデスクに座っていませんか?
- 余計なものをデスクに置いていませんか?
- 照明・音・温度は適切ですか?
これらのデスク環境にあてはまるものがあれば早急に改善が必要です。もちろん職場のルールや規定により自身ではどうしようもならない環境もあるかと思います。
それでも、できる範囲でデスク環境を整えることは、作業効率に大きな影響を与えるため結果的に査定や給与に関わるため、今すぐに力を入れて改善に取り組んでみましょう。
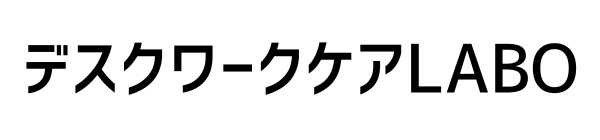

コメント